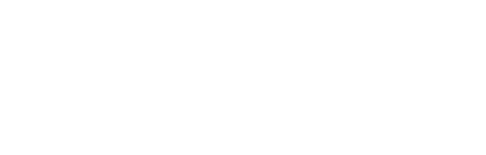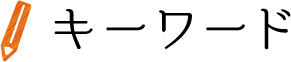小池由佳教授インタビュー 子ども食堂のこれからの未来
子どもが安心して食事ができる場所を作ろうと、新潟県内でも多くの団体が立ち上がり、子ども同士や親子同士、地域の人たちや支援者とのつながりの場を築いてきました。そんな矢先、新型コロナウイルス感染症が流行し、継続・運営での問題点や、その運営を支える側のさまざまな課題が見えてきました。新潟県立大学教授であり、「新潟こども食堂・居場所ネットワーク にこねっと」の代表も務める小池教授に、子ども食堂の現状と、これからの課題についてお話をお聞きしました。
-

-
profile
新潟県立大学 人間生活学部 教授
新潟ろうきん夢咲Club 幹事
小池由佳 教授
新潟こども食堂・居場所ネットワークにこねっとの代表を務める。専門は児童家庭福祉。新潟市内の複数の子ども食堂、新潟市子ども食堂ネットワーク会議アドバイザー、にいがた子ども食堂研究会の座長を務めている。
Q1 コロナ禍の子ども食堂はどんな様子でしたか?
コロナ禍でも活動を続けた団体が圧倒的に多かったです。みなさん「こんな時だからこそ、自分たちの役割を果たす時だ!」という気持ちが強く、会食に制限をかけなくてはいけない時期では、「お弁当配布でもいいのでやりましょう」と立ち上がっていました。現在は、新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類になったこともあり、徐々にお弁当配布から会食に戻りつつあります。他者とのコミュニケーションが極端に減った時期だったからこそ、そういった活動に救われた方も多かったのではないでしょうか。
Q2 今の子ども食堂に必要なことはなんでしょう?
継続すること、地域にあり続けることです。全国的にも関心が高まっているのもあって、支援面での継続は少しずつ増えてきていますが、実際に活動してくれる方たちが続けていけるように整えることも課題だと思っています。そのためには、活動する方たちも楽しんでやることが大切です。利用者の要望に全部答えようとがんばるのではなく、活動する団体、利用者、支援者がそれぞれ楽しみながらやることが継続へ繋がると思っています。
Q3 今後、地域の人が気軽にできる支援はありますか?
- 「支援」と聞くとハードルが高くなりますが、どんな場所か知ることも支援のひとつです。食事の利用をしなくても、「ちょっと様子を見せてください」と遊びに行くのも喜ばれると思います。興味が湧いたら、通ったり、手伝ってみてください。作った野菜などを持って行くのも歓迎されますよ。
-

「子供はしっかりご飯を食べる、楽しく食べる!」
それができるのが、子ども食堂の良さです。
- 現代は核家族・共働きの両親が増えていることもあり、子どもは親以外の大人と過ごす時間が減っている傾向にあります。いつもと違った環境で食卓を囲むことは子どもにとって新鮮ですし、大人にとっては食材の使い方や調理の仕方を知る機会になるのもいい刺激です。「一緒にご飯を食べる場所」だけではなく、そんな地域のコミュニティの場として賑わってほしいと思っています。また、「子どものことを考えて動いてくれていた大人がいたな」と子どもたちが覚えていてくれて、大人になった時にその行動ができる、プラスの循環を生み出してくれたらうれしいです。
-

前のトピックス
次のトピックス